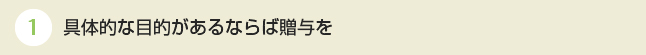 1具体的な目的があるならば贈与を
1具体的な目的があるならば贈与を
孫は目に入れても痛くないほど可愛いと言いますが、お小遣いをあげたりプレゼントを贈ったりと、我が子より孫のほうが可愛く財布の紐も孫に対しては緩いようです。
孫が「進学」という時期にもなれば、孫の親(自分の子)は住宅ローンや生活費に、教育費が加わり何かと出費がかさみます。こんなとき可愛い孫の未来のためにひと肌脱いでみてはどうでしょう。今回は祖父母から孫への相続・贈与を取り上げます。
一定の資産を譲り渡すには、相続と贈与の大きく2通りの方法があります。さらに贈与のなかでも「教育資金の一括贈与」という方法をとれば、非課税で贈与することができます。
【方法1】相続。ただし考慮すべき問題も
単純に「財産の一部を孫に遺したい」というのであれば、相続という形をとるのもよいでしょう。この場合、自分の子どもが健在ならば、法定上は妻と子どもが相続人となり、直接孫には遺産は渡りません。そのため、「遺言書」により孫を相続人に指定する必要があります。
ただし、相続を選択するときは、いくつか考慮すべき問題があります。一つは、孫が本当に必要としている時期に遺産が引き継がれるかどうかわからないということです。遺言書は書いても、いつ亡くなるかは誰にもわからないわけですから、たとえば受験や進学でお金が必要な時期に相続されないこともあるわけです。それだけではなく、遺言書に具体的な金額ではなく、財産の○分の○という比率で記載することがありますが、亡くなった時点で相続財産がいくらになるかわからないということもあります。
また、相続財産には相続税がかかります。相続人が未成年の場合は「未成年控除」がありますが、遺産額が大きくなればそれだけ相続人や扶養者の負担は大きくなりますから、被相続人(祖父母)はある程度、そのことも考慮して準備する必要があります。さらに、相続にはトラブルの心配もあります。特に遺言書による相続は、内容に納得しない人が出れば人間関係にヒビが入ることもあります。
【方法2】贈与。平成27年の改正で20歳以上の孫への贈与が有利に
例えば、孫が大学進学を控えている、習い事にまとまったお金が要るなど、具体的な目的があるならば、贈与という形式をとったほうが有利な場合があります。生前に贈与することで、孫の喜ぶ顔が見ることができれば、こんな嬉しいことはないですよね。
贈与税は平成27年1月の改正で、20歳以上の子や孫に対する「特例贈与」(表1)と、それ以外の「一般贈与」(表2)に分かれています。同じ孫でも年齢によって税率や控除額が異なりますから気を付けましょう。
また、贈与の目的を「教育資金」として明確に特化された場合は、1,500万円までは非課税で贈与できます。この教育資金については次のページを参照してください。
表1 子や孫が20歳以上の成人の場合(特例贈与)
| 基礎控除後の課税価格※ | 特例税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※その年の1月1日〜12月31日に贈与された財産の総額から基礎控除額110万円を差し引きます。
(例)21歳の孫が1,000万円の贈与を受けた場合
贈与税=(1,000万円-110万円)×税率30%-控除額90万円=177万円
残った贈与財産の額=1,000万円-177万円=823万円
表2 子や孫が20歳未満の未成年の場合(一般贈与)
| 基礎控除後の課税価格※ | 一般税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
※その年の1月1日〜12月31日に贈与された財産の総額から基礎控除額110万円を差し引きます。
(例)18歳の孫が1,000万円の贈与を受けた場合
贈与税=(1,000万円-110万円)×税率40%-控除額125万円=231万円
残った贈与財産の額=1,000万円-231万円=769万円
「相続時精算課税」とは?
「相続時精算課税」とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に生前贈与があった場合に、子・孫が選択できる制度です。贈与財産についてはいったん贈与税を支払いますが、相続時に贈与財産と相続財産を合算した額に対する相続税から、すでに支払った贈与税を精算することができます。通常の贈与の場合は110万円の控除となりますが、相続時精算課税には2,500万円の特別控除があり、贈与は何回でも利用することができます(ただし通常の贈与は利用することができません)。
2,500万円までは贈与税がかかりませんから、多額の資産を譲り渡す場合に有効です。
-
① 具体的な目的があるならば贈与を
















