会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者となり、自身で保険料を納付する必要はありません。しかし、第3号被保険者に該当しなくなったときには、本人が届け出て国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者へと切り替える必要があります。今回は、どんなときに3号から1号への切り替えの届出をするのか、届出をしないでおくとどうなるのかについて解説します。
1配偶者が退職したときや扶養から外れたときには届出が必要
第3号被保険者とは
国民年金の加入者のうち、厚生年金保険に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)は、第3号被保険者となります。
被扶養配偶者の認定基準は次のとおりです。
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(※1)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること
② ①に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(※1)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の状況を総合的に勘案して、第2号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められること
※1 障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
※2 この認定基準の実際の運用にあたっては、認定対象者が健康保険や共済組合等の被保険者として認定されている場合等には、これを尊重して認定することとしています。
第3号被保険者に該当する場合は、第2号被保険者である配偶者の勤務先を経由して第3号被保険者に該当する旨の届出をします。
第3号被保険者は個別に保険料を納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金保険の各実施機関が、国民年金制度に対して基礎年金拠出金として一括して負担しているからです。
第3号被保険者に該当しなくなるケース
第3号被保険者は、上で述べているとおり、「第2号被保険者の配偶者」に「扶養されている」ことで該当しますので、どちらかにあてはまらなくなれば、第3号被保険者の資格を有さなくなります。
第3号被保険者に該当しなくなるケースには、主に次のようなものがあります。
第3号被保険者に該当しなくなる主なケース
Bさん : 現在、第3号被保険者(Aさんの被保険者)
【ケース1】 Aさんが会社を退職して、自営業者になった。
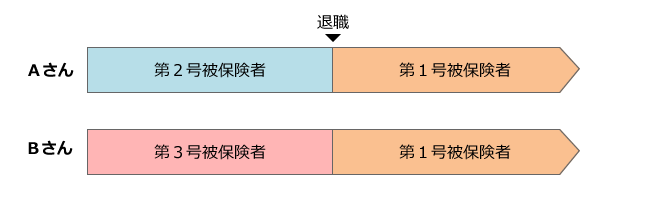
【ケース2】 Aさんが60歳で定年退職した。(BさんはAさんより5歳年下である。)
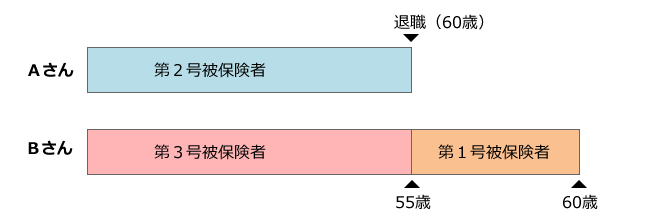
【ケース3】 Aさんは会社勤めを続けているが、65歳を超え、第2号被保険者ではなくなった。(BさんはAさんより10歳年下である。)
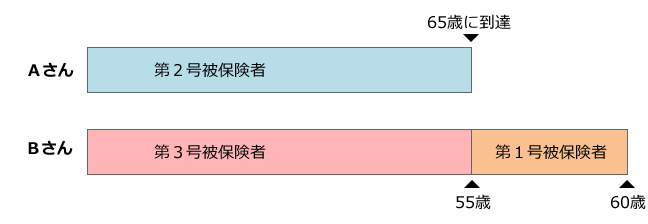
【ケース4】 Aさんが死亡した。
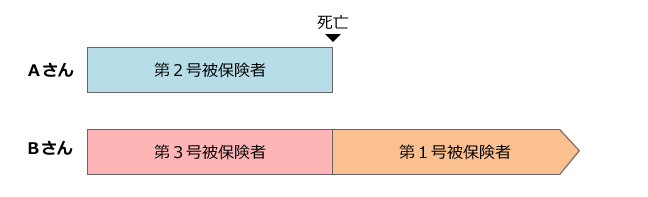
【ケース5】 AさんとBさんは離婚した。
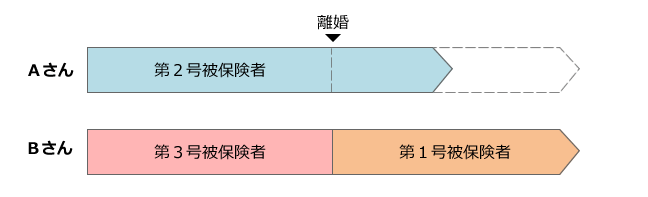
【ケース6】 Bさんの年収が130万円を超え、被扶養者から外れた。
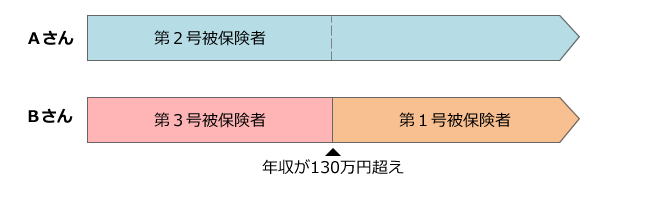
【ケース7】 Bさんが会社勤めを始めた(厚生年金保険に適用された)。
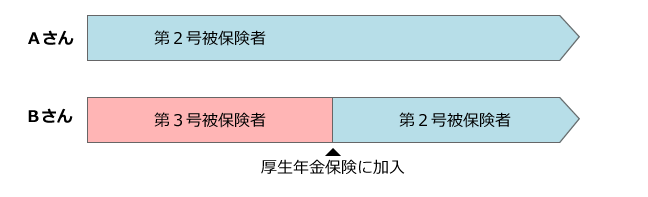
第3号被保険者に該当しなくなるケース
前記のケース7のような、第3号被保険者であった人が厚生年金保険に加入することによって第2号被保険者に変更される所定の手続きは、勤務先の事業所を経由して行います。しかし、ケース1~6のような、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きは、自分で届出を行う必要があります。忘れずに市区町村の窓口で「種別変更」の手続きをしてください。(ケース5・6の場合は、配偶者も事業所経由で届出を行う必要があります。)
このときの届出を忘れてしまうとどうなるのかについては、次項で解説します。
第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者が退職したり、自分の年収が増えて扶養から外れたりして、第3号被保険者の資格を有さなくなったときは、第1号被保険者に切り替える手続きを自分で行う必要がある
-
① 配偶者が退職したときや扶養から外れたときには届出が必要













