
妻と子ども1人をもつサラリーマンです。自分に万一のことがあった場合、残された家族の生活が心配です。遺族年金はいくらくらい出るのでしょうか? (38歳・男性)
遺族基礎年金は子どもがある配偶者(妻または夫)または子どもへ
遺族基礎年金は子どもがある配偶者(妻または夫)または子どもに支給されます。年金は定額です。子どもが18歳(1・2級障害がある場合は20歳)になったり、再婚した場合などは遺族基礎年金が支給されなくなります。
【遺族基礎年金】
条件
- ・亡くなった人が国民年金の加入者または受給者であること。
- ※60歳以上65歳未満に亡くなられた場合でも、日本国内に居住していれば、遺族は遺族基礎年金を受給できます。
- ・加入者の場合、次の保険料納付についての条件を満たしていること。
- ・死亡日の前日において国民年金の保険料を納めた(免除、猶予された)期間の合計が、保険料を納めなければならない期間※の2/3あること。
- ※「保険料を納めなければならない期間」とは、亡くなられた月の前々月までの期間をいいます。
- ・直近の1年間に保険料の滞納がないこと(2026(令和8)年4月1日以前に65歳未満で亡くなられた場合)
支給される人
子のある妻・夫、または子
年金額 ※2025(令和7年度)
- ・妻・夫が受給する場合:
831,700円(新規裁定者)、829,300円(1956年4月1日以前生まれの既裁定者) + 子の加算額
1・2人目 各239,300円 3人目以降 各79,800円 - ・子ども※が受給する場合:
1人目 831,700円(新規裁定者)、829,300円(1956年4月1日以前生まれの既裁定者) 2人目239,300円 3人目以降各79,800円 - ※子どもとは18歳到達年度の末日までの子、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。
妻・夫が受給している期間は子どもには支給されません。
受給期間
- ・子どもが18歳到達年度の末日を経過する(障害がある場合は20歳になる)前月まで
- ・再婚などにより遺族ではなくなる前月まで、など
- ※老齢基礎年金を同時に受給することはできません。

2人の子どもがそれぞれ18歳到達年度末日を過ぎたら加算額は減るの?
遺族基礎年金は18歳到達年度の末日までの子ども(障害がある場合は20歳未満の子ども)がいることが要件ですから、何人かいる子どものうち1人が成長して18歳到達年度の末日を過ぎたら(障害がある場合は20歳になったら)、その子どもの分の加算額はなくなります。末子が18歳到達年度の末日を過ぎた(障害がある場合は20歳になった)時点で遺族基礎年金は支給されなくなります。 子どもが亡くなったり、養子に出た場合なども同様です。
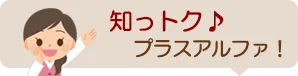
子どもがいない自営業の妻でも支給される年金がある
子どもがいない場合、国民年金だけにしか加入していない夫が亡くなった場合、妻は遺族基礎年金を受給することができませんが、こうした妻への救済措置として、国民年金には次のような給付あります。
寡婦年金
亡くなった人が国民年金の保険料を10年以上納めて(免除されて)家計を担っており、婚姻期間が10年以上ある場合に支給されます(夫に支給されるべき老齢基礎年金額の3/4、65歳まで)。
死亡一時金
亡くなった人が国民年金の保険料を36カ月以上納めており家計を担っている場合、①配偶者(妻または夫) ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹の順に受給できます。額は保険料を納めた月数に応じて12~32万円です。
※寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択します。
遺族厚生(共済)年金は子どもがいれば遺族基礎年金に上乗せ、それ以外は単独で
子どもがある加入者が亡くなった場合、厚生年金保険からは遺族基礎年金に上乗せして妻または子どもが遺族厚生年金を受給することができます。
子どもがない場合やその他の遺族は遺族厚生年金だけを受給することができます。
年金額は報酬比例部分(給料(平均標準報酬額)や加入期間により異なります)の3/4です。
【遺族厚生年金】
条 件
- ・厚生年金保険の加入者または受給者であること。
- ※60歳以上65歳未満に亡くなられた場合でも、日本国内に住んでいれば、遺族は遺族厚生年金を受給することができます。
- ・遺族基礎年金と同じ保険料納付についての条件を満たしていること。
- ※2015(平成27)年10月の被用者年金の一元化前は、遺族共済年金に保険料納付の要件はありませんでしたが、一元化後は同条件となっています。
支給される人
- ①妻、55歳以上の夫※1、子ども※2
- ②父母※1
- ③孫※3
- ④祖父母※1
- なお、一元化により共済組合等の転給制度(受給者が死亡等により失権した場合、次の順位の人が支給されるようになる)はなくなりました。
- ※1 夫、父母、祖父母の場合は60歳から支給されます。
- ※2 子どもとは18歳到達年度の末日までの子、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。
- ※3 孫とは18歳到達年度の末日までの孫、障害がある場合は20歳未満の孫をいいます。
年金額 ※2025(令和7)年度
- ・基本額 報酬比例の年金額※×3/4
- ・中高齢寡婦加算(18歳未満の子ども等がいない40歳以上の妻。65歳まで)623,800円
- ※報酬比例の年金額の計算については「いくらもらえるの? ②老齢厚生年金」をご覧ください。なお、加入月数は、最低300月は保障されます。
- ・経過的寡婦加算(1956(昭和31)年4月1日以前の生まれの妻。65歳以上)
生年月日に応じて 622,000~20,757円
支給される期間
- 遺族の条件に当てはまる限り、亡くなるまで。
30歳未満の妻の場合は5年間だけ支給されます。
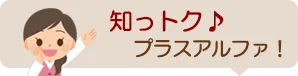
遺族厚生年金は自分の老齢年金と同時に支給されるの?
65歳になったとき、厚生年金保険や共済組合等への加入歴がない配偶者は、自分の老齢基礎年金と同時に遺族厚生年金を受給することができます。
65歳で自分の老齢厚生年金を支給される人は、老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の組み合せを選択することができます(金額が高いほうを選択)。
ただし、2007(平成19)年4月1日以後に遺族厚生(共済)年金が支給されるようになった人は、65歳以後は自分の老齢厚生年金を全額受給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。














